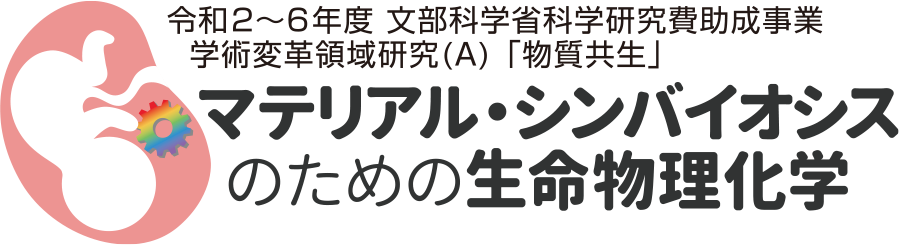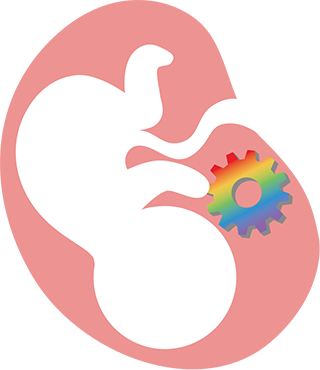1st International Symposium of Material Symbiosisの開催報告
九州大学 森 健
2023年3月30日に標記のシンポジウムを北大薬学部で開催した。コロナが世界的に終息に向かう中、久しぶりに海外から講演者をお呼びすることができた。マスクを外した講演者が活きいきと発表する姿を見るのは久しぶりであった。直前まで薬学会が同大学で行われており、一日、間をおいての開催となった。北大の生命科学系の研究拠点であるGI-CoREとの共催であり、会の運営の面でもご支援いただいた。基調講演は以下の4名の海外で活躍される先生にお願いした。また、本領域からの招待講演者として、山吉先生、大場先生にご講演いただいた。山吉先生からは、本領域の目玉の一つであるエクソソーム随伴型DDSをご紹介いただき、大場先生からは、PI3K-AKT経路のイメージング技術を駆使した解析についてご紹介いただいた。さらに領域の若手企画として、6名の若手教員と学生の皆さん(北大 小畑さん、長崎大 寺田さん、北大 勝山先生、東工大 中川先生、北大 藤岡先生、九工大 森本先生)にご講演いただいた。以下、基調講演の4名の皆様の講演を振り返ってみた。
Prof. Michael Rod Zalutsky (Duke大学)
Dr. Steve Roffler & Ms. Bing-Mae Chen (Academia Sinica)
Dr. Takashi Kei Kishimoto (Selecta Biosciences)
Prof. Jun Ishihara (Imperial College London)
Zalutsky先生は、GI-CoREの小川美香子先生が招かれた基調講演者である。あいにく日程が合わず、オンラインでのご参加となった。アスタチンの同位体(221At)をがんの放射線治療に用いる内容であり、豊富なデータをもとにご説明いただいた。221Atは、ベータ線よりも飛程が短く安全な放射線であるアルファ線を放出し、崩壊過程が単純で制御しやすく、さらに入手が比較的容易であるという特徴のため、現在、放射線治療分野で注目される元素である。これを低分子やミニ抗体などのがん標的リガンドに修飾して、前立腺がん、乳がんに対する特異性を付与した。これにより安全性と効果を両立することに成功した。
残る3名の先生は、私がお招きさせていただいた。本領域の趣旨に合う方を私自身の興味に基づいて選ばせていただき、大変ありがたく思った。Roffler先生は、PEG抗体の分野の巨人である。PEG抗体との出会い(DDS研究の失敗が発端)に始まり、そのユニークなDDSへの活用法の提案、コロナワクチン後に懸念されるPEGに対するアナフィラキシー応答について、豊富な成果をご説明いただいた。講演のタイトルを「続・夕陽のガンマン」から取るなど、西海岸の大学で学位を取られたのち、現在、台湾の国立研究所でPIをされているという経歴が物語るように、陽気なお人柄の現れたご発表と感じた。PEG抗体はロシュに相当な額でライセンシングされたとのことであり、失敗を失敗で終わらせないポジティブさとタフさを教えていただいた。
岸本先生は、ボストンのバイオベンチャーの研究者であり、寛容を誘導するナノ粒子製剤のアイデアを2015年に提案された(研究開始は2011年とのこと)。現在、取り組んでおられる酵素製剤やウイルス製剤に対する免疫寛容の誘導について、臨床試験の結果をお示しいただいた。アイデアの発端はハーバード大医学部の研究者にあり、それを短期間で実用化間近まで持っていくことのできる米国の実用化研究のダイナミズムを感じた。岸本先生は、日本でお生まれになってすぐに米国に移住されたため、日本語はほとんどお出来にならない。東海岸の大学を卒業されたのち、ボストンでバイオベンチャー3社を渡り歩いてこられた。飾り気のない控えめなお人柄であるが、実用化研究の厳しさを味わってこられたことと思った。実は、長谷先生と私も2015年ごろに、同様のアイデアで研究を始めようと考えていた。岸本先生の論文を見つけてがっかりした一方で、手本のような研究の展開に脱帽したものである。
最後に石原先生である。石原先生は、東大で学位を取られたのち、スイス、米国でPDを経て、数年前に英国の一流大学で独立された気鋭の若手研究者である。腫瘍に共通の性質(細胞外マトリックスの露出)を標的にしたがん免疫の活性化剤(サイトカイン、免疫チェックポイント阻害剤)についてご説明いただいた。一方で、アルブミンをリンパ節標的化のリガンドとして利用した免疫寛容の誘導剤(サイトカイン)もご説明いただいた。活性化も抑制も運ぶ物質次第である免疫の面白さを感じた。またいずれも実用化を強く志向した研究であった。
4名の先生の研究は、いずれもご自身で基礎から作り上げた実用化研究であるとの印象を持った。物質共生という研究領域を成功に導くためのロールモデルとなるであろう。幸い私たちは、基礎から応用までの幅広い研究者で構成されている。本気になりさえすれば、面白い研究のアイデアが出せるはずである。残り2年間で、本領域の研究者が協力して基礎と応用をつなぐ魅力的な成果を出さなければならないと改めて思った。
最後に、薬学会と連続で、本シンポジウムをお世話いただいた北大の皆様、特に、前仲研究室の皆様に感謝申し上げます。